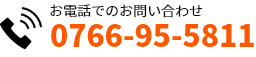- HOME >>
- お知らせ/ブログ >>
- 記事詳細
お知らせ・ブログ
■ 開発人生記_________機械工学を学んだことを生かして事業に必要な様々な機械を開発、その道のりを公開
開発人生記(その20) 地下室のお話(2話目)
地下室のお話(2話目)
過去のブログ「開発人生記 その18」で「地下室のお話」と題して、自宅で地下室を作り地下室環境の観察を続けていることを紹介いたしました。 このとき、日本の夏は湿度が高いので地下室は夏には湿度がほぼ100%となり、カビ対策に悩まされていることを報告しました。
近年は地球温暖化で夏が長くなり、猛暑日が格段に多くなった結果地下室のカビ発生が激しくなり、以前は6月から発生していたのが5月になり、床や巾木付近だけだったものが天井まで発生するようになってしまいました。
対策をしなければと考えた私は、いろいろな方法を検討しました。 一番ポピュラーなのはエアコンをつけて湿度と温度の両方を下げることです。 これにはいくつか問題点が有ります。 一つは室内機結露水の排出です。 地下室には排水管が有りませんので別途にドレンポンプを設置する必要が有ります。 また、電気代が結構かかります。 エアコンの除湿運転は通常の冷暖房よりも電気をよけい使うのです。
そもそも地下室は恒温性が高くエアコン不要というのが大きなメリットの一つです。 地下室にエアコンを付けてガンガン電気を使うのなら、高額な地下室築造はメリットが無いことになります。
次の方法として、家には井戸が有るので井戸水で冷やした空気を送り込む方法を考えました。 井戸水で冷やしたラジエーターの回りに空気を通して冷やせば当然湿度も温度も下がります。 これなら250Wの井戸ポンプと150W程度の送風機で済みますから、電気代も抑えられそうです。 しかし、この場合は設備を床下などの地上部に置いて、そこから地下室に除湿・冷却した空気を送り込む(又は循環させる)ダクトホースを配置する必要が有ります。 いろいろ図面を検討したり床下をめくって寸法を測定したりしましたが、ダクトホースを通すスペースをとるには廊下や部屋の一部の床を撤去する必要が有り、とても現実的ではないことが分かり断念しました。
そうこうしているうちに、「カライエ」というデシカント除湿機をダイキン工業が販売していることを知りました。 カライエは湿気を水として排出するのではなく高湿度の空気として排出する為、地下室に設置しても排水ポンプが不要になりそうです。 説明書では排気ホースは結露対策の為、下り勾配で配置するように書いてありましたが、地下室からの排気は下り勾配だけでは配置できません。 しかし結露は高温の空気が低温側に触れた時に発生します。 私の地下室は除湿が必要な夏場は通常外気より室内温度が低いため、排気ホース内で結露が発生する心配は無さそうです。 排気ホースは内径が40mm程度のフレキシブル管で、これ1本を外に出すだけで配管完了ですから、地下室からの配管も簡単です。
NETで価格調査すると、6万円台で購入できそうです。 そこで、地下室から外へ排気管を通す方法を検討しました。 地下室天井に穴をあけ、更にその穴の真上と思われる玄関横の物置内の床に穴をあけました。 ホースはフレキシブル管ですから多少穴の位置にずれが有っても通ります。 更に物置の基礎コンクリートに横穴をあけてそこにカライエの排気ホースを通すこととしました。 ホース内に虫が侵入しないような吐出口を付けて完成です。

5月に取り付け完了し、作動させてみました。 部屋内の温度・湿度は置いてあるデジタル時計で測定しています。 近頃の時計は温度・湿度も表示される上に大変お安くなりました。

カライエを動かしてみると、ファンの音が結構大きく感じます。 1日動かすと60%を超えていた湿度は60%以下となり、室温は2℃ほど上昇しました。 その後観察していると昼間に気温が上昇すると湿度は上昇し60%を超えますが夜間に気温が低下すると60%を下回るので夜間は電源を切るようにしていました。
ところが6月になると今年は一気に真夏となり、夜間も気温が大きく低下しないので湿度の低下も悪くなり、1日中つけっぱなしにしないと湿度を60%付近で維持できなくなったのです。 更に7月になると毎日猛暑日が続き、連続自動運転にしても時として湿度は63%~65%に上昇することが起こり始めました。 室温もどんどん上昇を続け、8月末には30℃程度まであがりました。

この除湿器には自動運転の他にもっと強力に除湿するパワフル自動やターボといった運転メニューもあります。 いちどパワフル自動を使ってみましたが、室温がますます高くなったので使用をやめました。

湿度は8月後半がピークで、室温は9月初めがピークとなりました。 カライエ無しの場合、湿度は100%近かったのですから、劇的な低下です。 室温はカライエなしの場合はMAX27℃程度でしたので、2℃~3℃上昇したことになります。
最高湿度は65%程度になりましたが半日程度で60%付近まで下がるので、カビの発生は殆ど無く、カビ除去作業からは完全に開放されました。 しかし以前のブログで紹介したように、私は地下室で柔軟体操や筋トレをしているのですが、室温は30℃近辺が1ヵ月以上続くのでさすがに暑く、扇風機を使っています。 室温は上がりましたが湿度が下がったので、扇風機を使えばなんとか今まで通りの運動メニューをこなすことが出来ています。
使ってみた結果、湿度低下効果は劇的なものがありますが室温上昇が欠点です。 高効率なペルチェ素子を開発して発熱面エネルギーをデシカントエレメントの加熱に使い、冷却面で室内還流空気の冷却を行って室温上昇を防ぐなどの技術開発で、湿度は低下するが室温は上昇しないような、もっと完成度の高い除湿機の出現を期待しております。